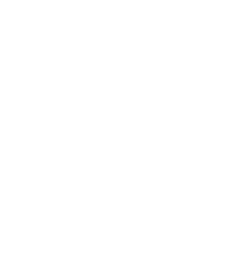7月
京都の街はもう祇園祭一色に染まります。
この祇園祭、別名「鱧祭り」とも呼ばれます。祇園祭の頃
骨切りと云う工夫を凝らした技で深い味わいを引き出しま
玄関や床の間に檜扇水仙を生け、鱧寿司と素麺と美味しい
そして忘れてはならないものが七夕素麺です。
盛り付けた素麺の中央にピンクとブルーの冷や麦を天の川
そして魚の鱚をkissとかけて、骨を取り結んで天ぷら
こんな創意工夫と共にお祭りを楽しみます。
今年から四条通りの歩道がグーンと広くなり、祇園祭の見
(今橋治楽先生より)
京都伏見アトリエ遊お煎茶教室
式年遷宮賜奉祝 葵祭煎茶献茶祭
京都伏見アトリエ遊お煎茶教室
京都伏見アトリエ遊お煎茶教室
3月 京都伏見アトリエ遊 お煎茶教室
3月 弥生
お花屋さんの店先には色とりどりの春の花が並び、何だかウキウキした気分になってきますね。
ひな祭り、ホワイトデー、卒業式、お彼岸とお花を飾る事も多くなります。
3月6日の「啓蟄」は冬ごもりしていた虫が這い出てくると云う意味で、私達も動き始めないといけません。
「 暑さ寒さも彼岸まで」と云う様に、お彼岸が済めば一気に春です。スタートの月を迎えます。その為にも今から準備をしておきたいものです。
お茶の方では、3月が一番自然の運行に敏感でなければならない月かもしれませんね。
冬でもなし、春でもなしと微妙な気候の変化の揺れに添った淹れ方が大切です。
(これが非常に難しいのです)
お茶の味の中にも春を感じられる3月、敏感でいたいものです。
京都伏見アトリエ遊 小川流煎茶教室
お菓子は「桃」です
京都伏見アトリエ遊お煎茶教室 2月
京都伏見お煎茶教室 初煮
京都伏見お煎茶教室
師走 一年を締めくくる大切な月です。
南座に吉例顔見世興行の「まねき」が上がると、京都の街はいよいよ師走の趣となり何だか気ぜわしくなってきます。
お歳暮、年賀状の準備をはじめ新しい年への準備に何かと忙しいものです。
こんな時、熱々の香ばしい香りのお番茶はひと息つくのにもってこいです。
お茶には再生するパワーがあります。… 薬としての側面も持ち合わせているのですね。
12月22日は冬至、ゆず風呂に入ったら一年を振り返ってみましょう。反省も出てくる事でしょう。
来年は未が来る年「未来」です。新しい年を希望に満ちた思いでスタートを切る為に、残りの日々をしっかりと締めくくりたいものです。
京都伏見アトリエ遊 お煎茶教室 今橋治楽先生
まるで讃美歌をうたっているようなお菓子です。
教室では1階がバイオリン教室 2階の和室がお煎茶教室となっています。